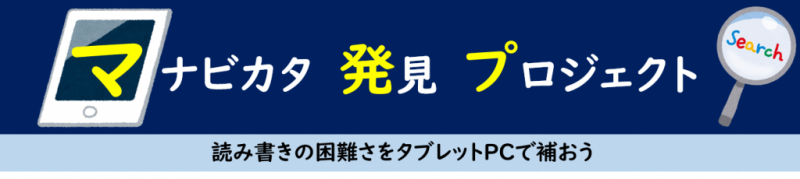0
0
0
3
4
3
1
読み書きに困難のある児童生徒の理解と支援
センター研究
特別支援教育グループ
(令和3~6年度)
センター研究の特別支援教育グループでは、「マナビカタ発見プロジェクト~読み書きの困難さをタブレットPCで補おう~」に取り組んでいます(令和3年度~)。本プロジェクトは、読み書きに困難のある児童生徒(*)に焦点を当てて、「自分に合ったマナビカタ(学び方)の発見」をサポートすることを目指しています。
*本研究では、全般的な知的発達に遅れがない児童生徒を想定しています。
研究成果物①
ガイドブック
| タイトル | 小・中学校の通常の学級における読み書きに困難のある児童生徒の学び支援ガイド(第2版) |
|---|---|
| 資料ダウンロード | 読み書きに困難のある児童生徒の学び支援ガイド(第2版).pdf 4493 |
| 表紙 |
|
|---|
| 概要 |
本ガイドは、小・中学校の通常の学級において、読み書きに困難のある子供たちがよりよく学ぶための支援のヒントになることを願って作成しました。 第1章「読み書きの困難への支援に当たって」では、読み書きの困難への支援の必要性について解説しています。 第2章「支援の考え方とポイント」では、赴任して間もない若手教師の新米(しんまい)先生の葛藤を描いた物語を追いながら、読み書きに困難のある児童生徒への支援の考え方とポイントを解説しています。特に、採用から概ね5年目まで(青森県の「教員の資質の向上に関する指標」における形成期)の先生方に、ぜひ読んでいただきたい内容になっています。 第3章「具体的な学び支援」では、読み書きに困難のある児童生徒が自分に合った学び方で学ぶことができるよう、代替手段としてタブレットPCを活用した学び方を中心に紹介しています。 第2版では、より多くの先生方にとって読みやすく、分かりやすいガイドとなるよう、主に第3章をリニューアルしました。 |
|---|
理解啓発研修コンテンツ
「学び支援研修」について
| 概 要 |
読み書きに困難(*)のある児童生徒への対応について考える協議を中心とした校内研修のコンテンツです。開発に当たって大切にしてきたことは、次の3点です。 ○「自分に合った学び方で学ぶ」という視点について共通理解を図ることを意図した内容とする。 *本研究では、全般的な知的発達に遅れがない児童生徒を想定しています。 |
| 対 象 | 教職員(小・中学校等) |
| 時 間 | 30~50分 |
| 進め方 |
こちらの資料を御参照ください。 |
研究成果物②-1
「学び支援研修」資料
| テーマ | 「自分に合った学び方で学ぶ」を共通理解 |
|---|---|
| 目 的 | 読み書きに困難のある児童生徒への対応について意見交換を行い、「自分に合った学び方で学ぶ」という視点について共通理解を図る。 |
| タイトル | No.1-1 「読む」のが困難な児童生徒への対応を考えよう |
| 進行用スライド | ①【進行:配付無し】No.1-1_読むのが困難(共通理解).pptx 131 |
|---|---|
| ワークシート | ②【ワーク:事前配付】No.1-1_読むのが困難(共通理解).pptx 88 |
| テーマ | 「自分に合った学び方で学ぶ」を共通理解 |
|---|---|
| 目 的 | 読み書きに困難のある児童生徒への対応について意見交換を行い、「自分に合った 学び方で学ぶ」という視点について共通理解を図る。 |
| タイトル | No.2-1 「書く」のが困難な児童生徒への対応を考えよう |
| 進行用スライド | ①【進行:配付無し】No.2-1_書くのが困難(共通理解).pptx 79 |
|---|---|
| ワークシート | ②【ワーク:事前配付】No.2-1_書くのが困難(共通理解).pptx 72 |
| テーマ | 「みんなでどうする?」を検討 |
|---|---|
| 目 的 | 読み書きに困難のある児童生徒への支援について考える協議を通して、「自分に合った学び方で学ぶ」という視点による支援を行う際の課題を解決する方策を検討する。 |
| タイトル | No.1-2 「読む」のが困難な児童生徒への支援上の課題解決に向けて |
| 進行用スライド | ①【進行/解説資料】No.1-2_読むのが困難(課題解決).pptx 94 |
|---|---|
| ワークシート | ②【KPTシート】No.1-2_読むのが困難(課題解決).xlsx 74 |
| 解説資料 |
|---|
| テーマ | 「みんなでどうする?」を検討 |
|---|---|
| 目 的 | 読み書きに困難のある児童生徒への支援について考える協議を通して、「自分に合った学び方で学ぶ」という視点による支援を行う際の課題を解決する方策を検討する。 |
| タイトル | No.2-2 「書く」のが困難な児童生徒への支援上の課題解決に向けて |
| 進行用スライド | ①【進行/解説資料:事前配付】No.2-2_書くのが困難(課題解決).pptx 78 |
|---|---|
| ワークシート | ②【KPTシート】No.2-2_書くのが困難(課題解決).xlsx 85 |
| 解説資料 |
|---|
| テーマ | 「みんなでどうする?」を検討 |
|---|---|
| 目 的 | 読み書きに困難のある児童生徒への支援について考える協議を通して、「自分に合った学び方で学ぶ」という視点による支援を行う際の課題を解決する方策を検討する。 |
| タイトル | No.3 読み書きが困難な児童生徒の周りの児童生徒への対応 |
| 進行用スライド | ①【進行/解説資料:事前配付】No.3_周りのこどもの理解(課題解決).pptx 87 |
|---|---|
| ワークシート | ②【KPTシート】No.3_周りのこどもの理解(課題解決).xlsx 64 |
| 解説資料 |
|---|
研究成果物②-2
「学び支援研修」補足資料
| 資料No. | 1 |
|---|---|
| タイトル | 「令和の日本型学校教育」の構築を目指して~全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現~(答申) |
| 著者/文献 | 中央教育審議会 |
| 資料ダウンロード | 1_「令和の日本型学校教育」の構築を目指して.pdf 90 |
| 資料No. | 2 |
|---|---|
| タイトル | 障害のある子供の教育支援の手引~子供たち一人一人の教育的ニーズを踏まえた学びの充実に向けて~ |
| 著者/文献 | 文部科学省 |
| 資料ダウンロード | 2_障害のある子供の教育支援の手引.pdf 194 |
| 資料No. | 3 |
|---|---|
| タイトル | 学校における合理的配慮 |
| 著者/文献 | 青森県総合学校教育センター特別支援教育課「『時々サクッと読み返したくなる!特別支援学級・通級指導教室の授業づくりに役立つQ&A』別冊 Q&Aと併せて読んでほしい資料」 |
| 資料ダウンロード | 3_学校における合理的配慮.pdf 287 |
| 資料No. | 4 |
|---|---|
| タイトル | 学習障害のある生徒に対する受検上の配慮の例(高等学校入学者選抜) |
| 著者/文献 | 文部科学省「高等学校入学者選抜における受検上の配慮に関する参考資料」 |
| 資料ダウンロード | 4_学習障害のある生徒に対する受検上の配慮の例.pdf 314 |
| 資料No. | 5 |
|---|---|
| タイトル | 教育の情報化に関する手引-追補版- |
| 著者/文献 | 文部科学省 |
| 資料ダウンロード | 5_教育の情報化に関する手引-追補版-.pdf 321 |
| 資料No. | 6 |
|---|---|
| タイトル | 小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 総則編 |
| 著者/文献 | 文部科学省 |
| 資料ダウンロード | 6_小学校学習指導要領解説 総則編.pdf 98 |